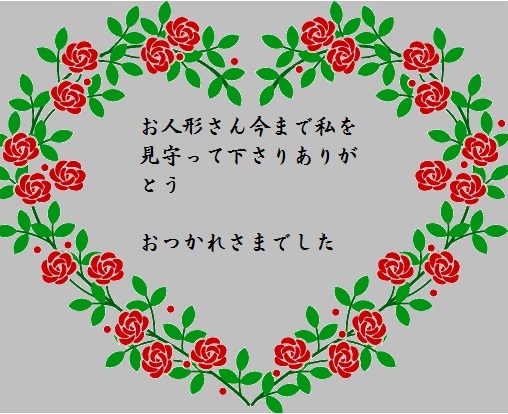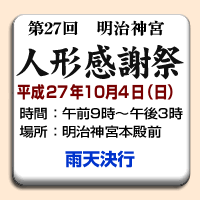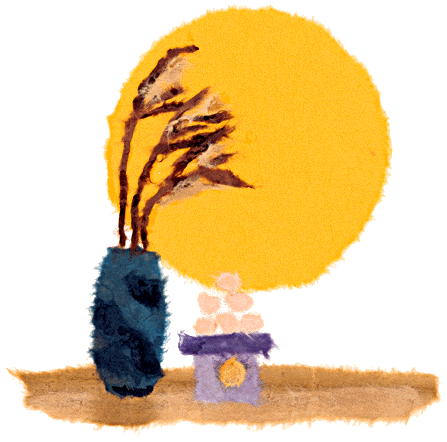人形のまちむ岩槻 工業団地隣接の蓮田地区のたんぼの畦道に咲く野菊
今、なかなか山野に出かけても見かけることが少なくなってしまいましたが、可憐に咲く野菊をみつけました。
イヌタデ(アカノマ ンマ)子供のままごと遊びに赤いごはんとしてよく知られている野草も一緒に顔を出しています。
ンマ)子供のままごと遊びに赤いごはんとしてよく知られている野草も一緒に顔を出しています。
また、数珠玉(すずご)もみかけなくなってしまいました。
数珠の様な玉、苞鞘(ほうしょう)が熟するにつれて光沢をもち固くなって緑色から黒色、灰白色に変化します。
糸に苞鞘を通して、首飾り、数珠、または袋に詰めてお手玉にした記憶のある方は多いと思います。
私もそんなままごと遊び、お手玉で遊んだものです。
とっても楽しかった思い出です。

(岩槻工業団地内)
赤ちゃん授乳室完備