雛人形を飾ってみたり、衣替えをしたりしてちょっと気分も変えてみたいです。

「重陽の節句」旧暦の9月9日は、新暦の10月半ば、菊の花の盛りの頃です。
江戸時代になると、五節句の一つとして『菊の節句』として一般に広まりました。
十月一日に行う衣替えを『後の衣替えのちのころもがえ』と同じく
ひな人形を春と区別して秋に飾るひな人形を『後の雛』と申します。

「後の雛」
女性の幸せの象徴であり、身代わり厄除けも意味する雛人形。
そして秋の収穫、敬老、長寿を祝うなど、実りの多き一年と人生に感謝する、秋。
春の一度きりではなく、「大人のためのひな祭り」として楽しみください。
重陽の節句に重ねた「後の雛」は桃の節句(ひな祭り)で飾った雛人形を、半年後虫干しを兼ねて再び飾り、健康、長寿、厄除けなどを願う風習。
大切なお雛様を半年後に出して虫干しをすることで、痛みを防ぐという暮らしの知恵でもありました。
資料 一般社団法人 日本人形協会より
破魔弓・羽子板、雛人形は2019年11月1日オープン予定です。


赤ちゃん授乳室完備








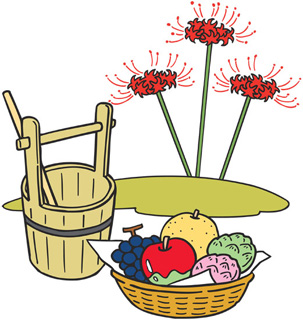 栗がごろごろっといっぱい入った栗ごはんは家族みんなで食べたいものですねぇ~。
栗がごろごろっといっぱい入った栗ごはんは家族みんなで食べたいものですねぇ~。



 今でも一部の地域に残る「流し雛」と、平安時代の貴族のお人形遊び「ひいな遊び」が結びついて生まれた「雛人形」。
現代では女の子の健康しと幸せを願い、3月3日のひなまつり(桃の節句)に飾ります。
今でも一部の地域に残る「流し雛」と、平安時代の貴族のお人形遊び「ひいな遊び」が結びついて生まれた「雛人形」。
現代では女の子の健康しと幸せを願い、3月3日のひなまつり(桃の節句)に飾ります。
 元々は中国の考え方で、九という陽数(奇数)が重なるため【重陽】と呼び、目出度い日とされてきました。
また菊の花は不老長寿に結びつくとされ、九日は菊の花を浮かべた菊酒などをたのしむ習わしです。
元々は中国の考え方で、九という陽数(奇数)が重なるため【重陽】と呼び、目出度い日とされてきました。
また菊の花は不老長寿に結びつくとされ、九日は菊の花を浮かべた菊酒などをたのしむ習わしです。


