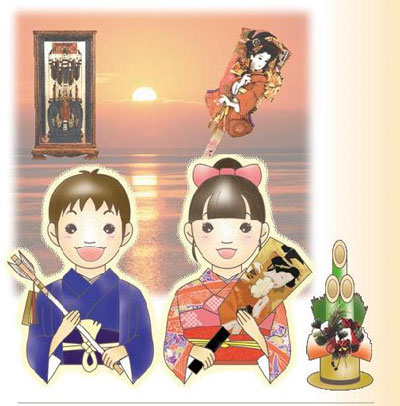お孫様の初正月飾りの破魔弓・羽子板、2016年度雛人形予約会を同時開催中

衣装着焼桐三段飾り 一番コンパクトサイズのおひなさま
京小十番親王柳官女付のおひなさま
(間口70cm×奥行57cm×高さ71cm)
欅の落ち葉が地面を彩る様子はだいぶ秋も深まったと言えます。
また、生垣の山茶花が心を和らいでくれるようです。
ひな人形の文様
ひな屏風
飛翔する丹頂鶴の刺繍がとっても豪華です。
飾り段の前板との共柄の仕様とし、とても素敵です。
『鶴は千年亀は万年』の長寿の象徴の鶴は品格のある文様として人気です。
ネットショップでお取扱い商品
羽子板・破魔弓:11月1日~12月29日
ひな人形:11月1日~2月24日
期間中は無休で営業いたします。


2016年度 雛人形予約会の開催中
初正月飾り、破魔弓・羽子板も同時開催中
(岩槻工業団地内)
赤ちゃん授乳室完備