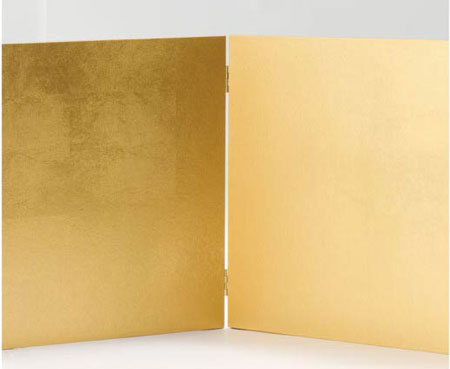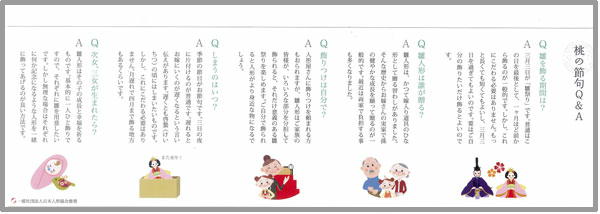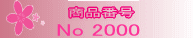
お子さまの健やかな成長を願う衣装の三段飾りのおひなさま。

サイズ 間口70cm×奥行56cm×高さ66cm

- 三段飾りのコンパクトなサイズの雛人形
- 衣装は鱗に宝尽くし文様てお子さまの健やかな成長祈願には皆様にお喜び頂いている人気商品です。
鱗文様
三角形の連続文様を鱗形とか鱗文様と呼ぶ。
鱗文様は大蛇の鱗であり、また龍(水神)の鱗でもある。
江戸時代から鱗文様は女子の厄除け、魔除けの文様として用いられる。
宝尽くし
もとは密教法具の一つ。先にとがった珠で火焔が燃え上がることもある。
これに祈ると何でも叶えられるという宝の珠のことで、如意の珠とも呼ばれます。
大きさの同じの同じ輪を円周の四分の一ずつずらしてできる図形。
四方への無限に広がることから連綿と続いて絶えないの意味を示す。
福の神の大黒天の持ち物として知られる。
振れば欲しい物が手に入り、望みが叶うという小槌。
物を打つことから敵を「打つ」に通じて吉祥文の一つ。
スパイスのグローブのこと。平安時代のはじめから舶来の香料として珍重される。
平安時代に輸入され、薬用・香料・染料・丁字油にもなり、希少価値から宝尽くしの一つになった。
悪ゃ煩悩を断ち切る知恵の剣。
着ると他人から姿が見えなくなる蓑。天狗が持っているとの伝えがある。
危険な事象から身を隠して護っていただける。
砂金や金貨を入れたもの。
絵巻物のような物を交差させて置いたもの。
昔はお経や絵巻ものが大切な宝物です。
物の重さを量る時に使うおもり、金銀で鋳で非常時に備えた。
弧状にくびれた形が文様として好まれている。熨斗(のし) 延壽の象徴。
誇張された弧を描く線が華やかな図をつくり、めでたさを表現。
土蔵の戸などに付けてある落とし鍵を外すのに用いる鍵。
江戸時代の宝尽くしに鍵が付け加わった。
- お顔は自然に微笑みたくなる笑みのある人気のお顔です。
- 緋毛氈に金屏風でシンプルにお飾りできます。

羽子板・破魔弓: 年内は12月29日まで 新年は3日から
(12月30日~1月2日はお休みとなります)
ひな人形: 11月1日~2月24日
期間中は無休で営業いたします。


 雛人形・五月人形 人形のまち岩槻 小木人形〒339-0072 埼玉県さいたま市岩槻区古ケ場2丁目 岩槻工業団地内
雛人形・五月人形 人形のまち岩槻 小木人形〒339-0072 埼玉県さいたま市岩槻区古ケ場2丁目 岩槻工業団地内
赤ちゃん授乳室完備
![]()