端午の節句 (五月人形)
五月人形の意味を知ったら、それならと鎧兜に鯉のぼりを飾ってくれました
男の子が強く、元気に育って欲しいと、願う行事
端午の節句には、屋内に鎧・兜・武者人形・破魔弓を飾り、また戸外では鯉幟・幟旗を立て、菖蒲を軒に挿し、粽・柏餅を食し、そして菖蒲湯に入って、菖蒲の枕で寝る。
五月は一年中の中で一番気持ちの良い気候。
秋に蒔いた麦も冬の麦踏に耐えて穂を出し、やがて穂も熟れ、芳しい匂いの中に畑も一面に黄色に変える。若葉も生き生きと茂る。
こんな季節の端午の節句、心弾む喜びの日です。
端午の節句の由来とは
端午とは語源は「初めの五」の意味で、もともとは「端五」と書き、「五」と「午」とは同音であるため「端午」と書くようになりました。
端午とは、月初めの
日本人は古代からもともと農作業(主として稲作)を生業とし、自然との関わり大切にしてきました。
農作業は最も重要なのは田植えで吉祥的な扱いをされます。
昔は田運びは男の仕事、田植えは女の仕事で神事につながるものです。
下図のように
手甲脚絆に赤のたすきの装いは『お田植え祭り』の神事の様子です。

端午の節句は早乙女(田植えをする乙女=田の神に仕える巫女と考えられていた。)が田植えに備えて家に籠もって、菖蒲を束ねて、軒下に挿して田の神様を祀る、女の人の節句の日でした。

それに古代中国では5月5日の祝日の日に、菖蒲(サトイモ科の植物)の草を摘み、お酒を作って飲み、病気にならないよう、また災厄を避けられますようにと祈った風習がありました。
その二つが結びついとされます。どちらも菖蒲を道具として使っていました。
日本でも薬草の菖蒲には邪気を祓う力があると信じられていました。
そこで5月5日には菖蒲を軒に挿して家から邪気を払ったり、菖蒲湯に入って病気にならないようにと、祈ったのです。

王朝時代、五月五日は宮廷では「菖蒲鬘(あやめのかつら)をつけてで節会いわゆる大宴会があり、邪気を防げるということから、菖蒲の薬玉を身につけて、「騎射(うまゆみ)」の行事もおこなわれました。
武家社会になります、武士の表道具の甲冑を梅雨に先駆けて虫干しをするために飾るようになりました。
この虫干しは定着してゆくことになり、「菖蒲」には同じ響きの言葉に勝ち負けを競う「勝負」や武士の男児らしき「尚武」に通じているということから、男児の、無事に成長し、強い立派な子になって欲しいとの願いにこめての祝いとなり、お祭りへと変化しました。
五月人形にはどんな飾り方があるのかしら
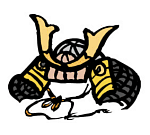
はじめは、菖蒲で武者人形を作り戸口に吊るしましたが、やがて人形師による武者人形を室内に飾るようになりました。
武家社会の中では当然、身を護る防具の鎧・兜はとても大事なものです。
武家社会の実践的な価値の鎧・兜と言う戦い目的でなく、現代では男児出生の祝いには無事に成長し、強い立派な子になって欲しい、その願いのもとに鎧・兜を飾ります。
五月の幟と言うと、鯉幟に武者絵幟がございます。

幟はもともと神様が天国から下界へ降りられる時の目印のために立てらたものです。
吹流しの意味は、やはり、神主さんのお祓いの大麻(おおぬさ)と同じ、身についた罪や穢れを祓って下さる道具として考えられています。
五色の吹流しは続命縷(ショクメイル・五色の糸で作られた薬玉)の五色糸の邪気払いが元になっているようです。
武家は幟や吹流しを邸前に立てて、町人は武家に習い吹流しを立てるようになりますが、やがて縁起の良い鯉の形にしたものを立てるようになりました。
江戸時代には、様々な図柄の幟が外に立てられた。武者絵・鍾馗・神功皇后・牛若丸・弁慶・金時などが描かれています。今でも小型化したものもいろいろとあります。
一般的に多くは鯉幟を飾る。”鯉の滝のぼり”と言われ立身出世の象徴の鯉(勝ち上がる出世魚)に定紋をつけた吹流しが子孫の繁栄を願う心に適うのでしょう。
ところで中国から来ている言い伝え”登竜門”とは、中国の黄河に竜門というところがあって、鯉がその急流を登りきれば竜になるという故事です。
鯉は生命力が強く、活力があり、どんな急流も泳ぎ上がっていく力強さを持つ魚です。
中国の黄河の上流に竜門と呼ばれる急流があり、ここに多くの鯉などの魚がたくさん集まり、さらに上流へとの思いでひしめいている。
この狭い激流を乗り切って上にと上がるのは非常に難しく、この急流を乗り切って登ることのできる魚は龍となることが出来ると伝えられています。
その鯉にあやかって、端午の節句には五月人形と共に鯉のぼりを立て、男の子の成長と出世を祈り願ってきました。
♪ 柱の傷はおととしの五月五日のせいくらべ
ちまき食べ食べにいさんがはかってくれた ♪
お供えもの、ほかいろいろな話し

- ■「粽」
- 5月5日に昔中国で屈原(くつげん)という政治家であり詩人でもある方を偲んで粽で供養した中国の風習が日本に伝わりました。
- ■「柏餅」
- 柏の葉はなかなか枝から落ちないという縁起の良いものとされ、柏の木には葉守の神が宿ると信じられ、祝いの行事と結びつきました。
また、邪気を払う願いをこめて端午の節句に食するとされています。
一緒に作ろう♪ 電子レンジで簡単!てづくり柏餅のご案内
◆ おこさまと作る手作りの柏餅 ◆
- 柏の葉はなかなか枝から落ちないという縁起の良いものとされ、柏の木には葉守の神が宿ると信じられ、祝いの行事と結びつきました。
- 「菖蒲湯」

- 菖蒲の節供と言われる如く店先にはヨモギと一緒に束ねた菖蒲が売られてる。
5月5日に菖蒲湯に入ると夏バテしない、また夏の虫に刺されないと、香り豊かな湯に入る習慣がある。
また、菖蒲の葉は鋭く剣のような形をなし、ヨモギと同様に高い香りのあることから、災いを除け、邪気を払う力があると言われております。
菖蒲の根元の赤みのある部分は大事です。つけたままの状態で湯に浮かべます。
- 菖蒲の節供と言われる如く店先にはヨモギと一緒に束ねた菖蒲が売られてる。
端午の凧揚げ
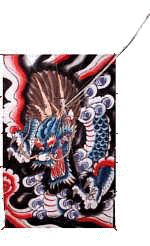
凧と言うと独楽(こま)と同様正月の男児の遊びのようだが現在でも関東から以西中部地方にかけて端午の節句として大凧をあげ、その年に生まれる初節句を迎える子供たちの健康と幸福な成長を願う行事として残っています。
例えば、埼玉県の今の春日部市(旧庄和町宝珠花)では日本一「百畳敷庄和の大凧」として江戸川の河川敷で毎年5月3日と5日に開催されています。
また静岡県の浜松市の町内対抗の凧揚げ合戦も有名で5月3日から5日にかけて 初節句の祝としての意味大きく「初凧」として男子の誕生を遠州灘を背景に勇壮に揚げる行事です。その他各地でいろいろ開催されているようです。

是非、ご家族お揃いで店内の数多い五月人形のご観賞を兼ねて、お気軽にご来店下さい。
店主ほか一同、心からお待ち申し上げます。
なお、ご来店には、後ページの交通案内地図をご参照下さい。
新着情報

竹虎雀飾り黒小札赤糸威之大鎧模写のご案内です。ー 雛人形・五月人形 小木人形 埼玉 人形のまち岩槻ー
強靭な地下茎は長生きの象徴の竹 鎧の大袖には竹に虎雀金物、兜には竹の鎧飾り 七月に入りました。 五節句の一つ「七夕の節句」がございます。 […]

2025年7月1日『氷室の節句』ー 雛人形・五月人形 小木人形 埼玉 人形のまち岩槻ー
旧暦6月1日に行われる行事で、冬に貯蔵した氷を食べることで暑気払いをする風習 『氷室の節句』には将軍や天皇が暑気払いとして、氷の上に小豆あんを乗せた氷餅を食べたそうです。 三画の形に赤い小豆 […]

小木人形 2025年7月の営業日のお知らせです =小木人形 埼玉県 さいたま市 岩槻=
小木人形を毎度ご愛顧いただきまして、有難うございます。 あと数日で暑さ厳しい七月を迎えます。 皆様はお変わりなくお過ごしでしょうか。 七月も引き続き土曜日・日曜日・祝日はお休みにさせて頂 […]

雛人形の歴史を知りたい 「立雛から座雛へ移る時代背景」=小木人形 埼玉県 さいたま市 岩槻=
雛は立雛たちびなと座雛すわりびなに分類されます。 立雛は歴史は古く、紙雛とも呼ばれます。 上巳の節句、雛遊と、雛の対象が貴族、武家にとどまっていたころは立雛です。 座雛は寛永 […]

雛人形の歴史を知りたい 「京都から江戸へやってきた雛祭」=小木人形 埼玉県 さいたま市 岩槻=
寛永の末期に民間で雛遊びが定期的(三月三日)に行われる 京都で生まれた雛遊はあくまで貴族社会の縮図 京都の雛遊を江戸へもたらした一人として春日局と言われます。 京都から江戸へ雛遊が移入され、民間でも三月三 […]




